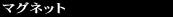
| 『マグネット』 | |
|---|---|
| 初出誌 各項目参照 | |
| <単行本> | |
| 幻冬舎 1999年(平成11年)4月10日発行 | |
| 256頁/ISBN:4-87728-291-2 | |
| あとがき/258〜261頁 | |
| <文庫本> | |
| 角川文庫 1987年(昭和61年)11月10日発行 | |
| 214頁/ISBN/4-04-1711001-4 | |
| あとがき 215〜217頁 解説/富岡幸一郎 | |
| 『4U』以来、約一年半ぶりの新作短篇集である。詠美の短篇を読んでいてまず思うことは、読後感が気持ち良いところ。まるで切れ味の良いナイフのようなものなのだ。本人も、オチのない短篇は書きたくないとインタビューなどで言っているが、今回も、最後の一文が読みたいがために読み進めていった。
今回は、殺人、連続放火、覗き、結婚詐欺など、新聞の社会面に載りそうな事件を題材にしながら、男女の関わり合いを描いた9編の作品が収められている。 「熱いジャズの焼き菓子」 初出誌『新潮』98年1月号128〜138頁 つきあい始めて1年もたつというのに、自分のことを“みどり”という下の名前で呼ばず、“黒木”と名字で呼ぶ泰蔵は、ある日、みどりに重大な告白をする。「おれ、今日、人を殺して来ちゃった」と。そして、みどりはしばらく彼をかくまう。読んでいない人のために、これ以上は書けないが、それほどまでにこのラストのオチは鮮やかで、ささやかな女性の心理がうまく描かれていると思う。 「解凍」 初出誌『文學界』98年9月号46〜57頁 俊也の大学時代の同級生早川が連続放火で捕まり、物語は敏也の回想を軸として語られる。その回想の中の早川にはすでに連続放火の犯人を思わせる言動がエピソードとしてあらわれており、何故か、少し恐いような、切ないような気分になる。 「YO−YO」 初出誌『文學界」98年1月号64〜73頁 男と女の高尚な駆け引きといった感じの短篇。美加は会社の新年会の帰りに一人で立ち寄ったバーで知り合った若いバーテンダー門田と一晩を共にする。そして、帰りがけに数枚の一万円札を置く。つまり、彼女は男を買ったのだ。次に会った時、今度は門田が彼女を買った。だが、クリップに挟まれた一万円札は一枚減っていた。憤った美加は3度目に会った時、さらに一枚少ない一万円札を渡す。このようにして枚数が減っていくたびにお互いの距離が縮まっていくことに気づく。美加と門田の関係が、「共同作業」という言葉をキーワードにして描かれている。この本の中では一番静かな作品と言えよう。 「瞳の致死量」 初出誌『新潮』98年8月号90〜99頁 ニューヨークに住む二人のカップル。ダンケとメルシーの趣味は覗き。ところが、この物語を語っているのは、その二人を覗き見ている「私」である。レンズはあくまでもこの二人に向けられているが、ナレーションは「私」である。ただ「私」が何物かであるかは一切明らかにされていない。別のビルから覗いている人物だとするとこの中で書かれているような二人の会話までは(盗聴でもしていない限りは)聞こえるわけはないから、恐らく二人の部屋の中にある「物」もしくは「神様」の目なのかもしれない。 「LIPS」 初出誌『文學界』98年5月号18〜28頁 結婚詐欺を題材にした話。この話のおもしろさは、騙す方の男の言い分と、騙された方の女の言い分が交互に綴られているという点。正確に言えば、取り調べ官とのやり取りが、男側女側交互に描かれている。手法的には『チューイングガム』と似ている。取り調べ官との掛け合いのような問答が、ときには哲学的なもののように思えて面白かった。 「マグネット」 初出誌『オール讀物』98年1月号50〜60頁 構成的には「解凍」と似ている。中学の時の先生が女子生徒に強制猥褻をした雑誌記事を見た由美子が、その先生と関っていた頃のことを回想する。由美子はその先生を自ら誘惑したことがあるのだ。先生が社会科の先生であり、世界地図やピカソなどが小道具となってラストに流れ込む作風は、やっぱり詠美は短篇の名手と思わせる。 「COX」 初出誌『新潮』99年1月号154〜164頁 久々にゲイを題材にした作品。でも、これは「ヴァセリンの記憶」や「GREEN」のようにゲイを直接的に描いているのではなく、タイプ的には「個人の都合」に似ており、ゲイを間接的に第三者の目で描いている。主人公は、ニューヨークに住む、どちらかというとお堅い感じのビジネスマン、ウィリアム。彼がフランスに留学している妹を訪ねてパリに来てみると、彼女は長かった金髪を坊主頭すれすれまで短く刈り、「COX」というゲイバーで働いていた。最初はパリのゲイ達に嫌悪感を抱いていたウィリアムは、常に自分に正直な彼らと、そんな彼らの人気者である妹を少しずつではあるが理解するようになる。「トラッシュ」に出てくるバッキーにしても、「個人の都合」に出てくるデイヴィッドにしても、今回登場するオリビエにしても、詠美の描くゲイ達は皆素敵だし、詠美自身も彼らを心から愛しているのが良くわかる。この作品の中で、あちこちの工事現場に姿をあらわす、ある一人の労働者が男を欲しがる種類か、女に体を熱くする性質なのかを知りたいと思い、オリビエと妹が工事現場に出向くシーンがあるが、これは実話に基づいており、『熱血ポンちゃんは二度ベルを鳴らす』「ポンのパリス イズ バーニング」p51に詳しく書かれている。 「アイロン」 初出誌『群像』98年11月号148〜158頁 実験的小説かもしれない。とにかく主人公の思考がそのまんま描かれているのだから。これは「この世の中で一番自由なのは、脳みそなのではないか、と私は思う」から始まり、会社での「私」の行動、「私」の甘い夢、ショウウィンドウ内のグッチ、それを盗む想像から取り調べの時のカツ丼に思いは及び、果てははげのおやじからニコラス・ケイジまで話は続く。しかも、満員電車の中で見かける気になる男を見つめる「私」は想像の中でニューヨークのサブウェイに乗っている。まるで連想ゲームのように話が展開するが、私はこの話が何故かとても好きだ。自分も似たいような思考回路を持っているからだろう。 「最後の資料」 初出誌『文學界』99年1月号68〜77頁 あとがきでも本人が書いているように、この作品は、彼女の義弟のことを書いている。恐らく他の8編のいくつかは、この短篇に描かれていたように書かれたものであろう。詠美の作品には死を扱ったものがいくつかあるが、いつも思うのは、常に客観的な視線で死を描いているだけに、読者の胸に響くところがあるということ。今回も淡々としていながらも、静かな悲しみが読後感として残る。 参考文献/インタビュー 「読売新聞」’99年4月3日夕刊 (4)/「ダヴィンチ」’99年5月号など |