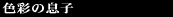
| 『色彩の息子』 | |
|---|---|
| 初出誌 各項目参照 | |
| <単行本> | |
| 新潮社 1991年(平成3年)4月20日発行 | |
| 199頁/ISBN:4-10-366804-0-3 | |
| あとがき 201頁 | |
| <文庫本> | |
| 新潮文庫 1994年(平成6年)6月1日発行 | |
| 201頁/ISBN:4-10-103613-6 | |
| あとがき 202頁 解説/筒井ともみ | |
| 女性誌、『SPUR』に一話完結の形で連載された短編集である。タイトルを見てもわかるように、「色」がテーマとなっている。「カンヴァスの柩」でも詠美は色えのこだわりを見せているが、この短編集では、さらにその色を意識した作品を書いている。本の装丁にもこだわりが見られ、何ページかごとにその作品に相応しい色紙が挟み込まれているのだ。しかも単行本だけでなく、文庫本にも同じような工夫がほどこされている。この「色彩の息子」は、「ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー」や「フリークショウ」といった、いわゆる男女の恋愛を描いた短編集とはまったく違った作風で、「蝶々の纏足」や「風葬の教室」と同じ路線といえよう。また、「ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー」などはエンタテインメント性が高いのに対し、「色彩の息子」のような作品はどちらかというと純文学の要素が強い。そこに山田詠美ワールドの幅の広さを感じる。 「陽射しの刺青」 初出誌 前編:『SPUR』1989年10月号122〜125頁 後編:『SPUR』1989年11月号100〜103頁 三島由紀夫の「午後の曳航」を彷彿とさせる作品である。詠美は三島の作品を愛読しており、この作品にはその影響が色濃く出ている。詠美の三島へのこだわりについてはインタビュー「三島・船乗りフリーク」 (聞き手 富岡幸一郎)『すばる』1988年11月号180〜185頁に詳しい。また、島田雅彦との対談「非同時代としての三島」(『内面のノンフィクション』収録)がある。 「声の血」 初出誌『SPUR』1989年12月号 94〜97頁 国雄は、父親が連れて来た新しい母親と肉体関係を結んでしまう。彼は彼女の声が自分にのしかかってくるのを感じていた。自分のあちこちについた彼女の口紅のあとを、彼は声の血だと想った。結末が鮮やかな短編小説。 「顔色の悪い魚」 初出誌『SPUR』1989年1月号 90〜93頁 恋人と別れた女が、明け方のさびしさに耐え切れず、悪戯電話をする話。詠美が得意とするその場の空気の描写が秀逸である。 「高貴なしみ」 初出誌『SPUR』1989年4月号 <調査中> 高校二年生の「おれ」には健一という親友がいた。小さな頃に父を失くし、母の手で育てられた「おれ」と、何の不自由もなく育った健一はお互いに正反対の境遇であるが、それがゆえに仲が良かった。健一はすみれという他校の男たちの間でも有名なほどの美人と付き合い始めてから二人の関係が崩れていく。男のコンプレックスの裏側を描いた作品。 「病室の皮」 初出誌『SPUR』1989年3月号 <調査中> 自分が自意識過剰な人間であることを知り、そのことで悩んでいる女の話。親友の和江に新しい恋人ができ、その彼を紹介される。和江にたのまれて三人で会うようになるが、ある時、彼女は彼を好きであることに気づき、そして彼もまた自分を好きであることを知る。 「草木の笑い」 初出誌『SPUR』1989年2月号 96〜99頁 女を強姦したとして取調べを受ける男の話。あるクラブでホステスとして働いていた礼子は、まるで植物のような女だった。 「白熱電球の嘘」 初出誌『SPUR』1989年7月号 98〜102頁 誇大妄想癖のある女の悲哀を描く。幼い頃から人を感動させるために自分が悲劇のヒロインであると嘘をついてきた祥子は、クラブのホステスのアルバイトを始め、ある男と恋に落ちた。これも結末のオチが鮮やかである。 「ヴァセリンの記憶」 初出誌『SPUR』1989年5月号 86〜89頁 大学の美術部に所属している「ぼく」は、部のアイドル的存在の礼子からある相談を受ける。彼女は4年生の池田先輩のことが好きなのだが、彼に冷たくされた。そこでその理由をきいて欲しいというのだ。彼は池田先輩と会うが、別れ際にキスをされてしまう。その後、「ぼく」は礼子と付き合うようになるが、何か釈然としなかった。「GREEN」や「個人の都合」と同様にゲイの世界が出てくる。 「雲の出産」 初出誌『SPUR』1989年6月号 82〜85頁 スノビッシュな連中の集まるグループの中に、とし子という名の冴えない女の子が加わった。みんなから嘲笑されながらも、一向にそれに気づかない彼女のことを皆はうっとうしい雨雲のようなことから、雲ちゃんと呼ぶようになった。ある時、仲間で一番美しい男の玲がちゃんと寝るかどうかという賭けが行われる。美醜にまつわる人間の残酷な面を描き出している。 「埋葬のしあげ」 書き下ろし 金持ちの家に生まれた信介は、三人兄弟の仲で一番出来が悪かった。自分は価値のない人間だと思っていた彼は、ある夜、お手伝いの一人である恵子と話をする。どこか太宰治を思わせる作品である。 「黒子の刻印」 書き下ろし 梨花には双子の妹がいた。しかし双子でありながらも二人には決定的な違いがあった。梨花は自分の左頬の黒子と顔のバランスの悪さをコンプレックスに思っていた。劣等感を持っている女性の悲しみを描く。 「蜘蛛の指輪」 書き下ろし 狂人となってしまった母親を見守る息子の話。他の家とは雰囲気が違っている賢一の家族の様子が、気の狂ってしまった美しい母親を中心に描かれている、やるせない物語である。 |