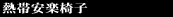
| 『熱帯安楽椅子』 |
|---|
| 初出誌「「すばる」1987年(昭和62年)4月号 32〜89頁 |
| <単行本> |
| 集英社 1987年(昭和62年)6月10日発行 |
| 164頁/ISBN:4-08-772607-X |
| <文庫本> |
| 集英社文庫 1990年(平成2年)6月25日発行 |
| 166頁/ISBN:4-08-749592-2 |
| 解説/森瑤子 |
| 私事ではあるが、今まで30年以上生きてきて読んだ、多くの本の中でももっとも好きな本である。無人島に一冊だけ持っていっていいといわれたら、迷わずこの本を持っていくだろう。 ストーリーは別にどうということはないのだが、文体が素晴らしいのだ。読み進めていくと、文章の中に体が沈みこんでいく感じがして、気持ち良い。二度目の大学の時に卒論でこの作品を扱ったせいもあるけど、恐らく100回は通しで読んでいるだろう。 初めてこの本を読み始めたのは、確か2月頃のこと。でも、途中まで読んで、急に本をパタンと閉じてしまった。読み終わるのが嫌だったから。これを読むのはもう少し暖かくなってからにしようと想ったのだ。結局もう一度きちんと読んだのはゴールデンウィークの間の休みの日だった。あたたかい日差の中で読み終わった時、この小説を何の苦労もなく読める日本人に生まれたことを神様に感謝した。そして、僕が会社を辞めて大学に入り直したのも、この小説で卒業論文が書きたかったからだ。以前詠美さんに、その話をして、「僕の人生を狂わせたのは詠美姉さんの『熱帯安楽椅子』なんだから、責任取ってください!」と冗談めかして言ったら、爆笑された。 偶然にも僕はこの小説を読む前にバリ島に行っており、この小説に出てくるデンパサールも、ガラムも、タナ・ロットの夕陽も、ガムランも、体で知っていた。だから、余計にこの作品には愛着があったし、運命的なものまでも感じてしまったのだ。もちろんそれ以来バリ島に行く時は必ずこの本を持参する。 僕の部屋には7冊の『熱帯安楽椅子』がある。2冊が単行本で、5冊が文庫本。どういうことか。ときどき僕は「熱帯安楽椅子病」という病にかかることがある。これは発作的に無性に『熱帯安楽椅子』が読みたくて読みたくてたまらなくなるのだ。たまたまそれが外出先だったりすると、近くの本屋に飛び込んでこの本を買い求めてしまうのだ。家に何冊もあるのを知りながら!!かくして『熱帯安楽椅子』が7冊も本棚に並ぶことになる。 ある友人が僕の持っているボロボロになった文庫本を見てとても驚いていた。表紙は破れてセロハンテープで補強され、ページを開くとぎっしりと蛍光ペンやボールペンでマークがしてあるのだ。そんなふうになるまで本を読む人を彼は知らないという。 ここまで読みこんでいると、すでにストーリーを全部把握しているのだが、何度読んでも新たな感動が生まれる。やはり、それはこの流麗な文体のせいだろう。私の『熱帯安楽椅子』の楽しみ方は、普通の人とはちょっと違う。最初からきちんと通して読むのは、年に数回で、後は適当にページを開いてそこから読むのだ。まるで詩を読むように。ストーリーを楽しむというよりも、文章を楽しむ感じといったほうがいいだろう。 初めて読んだ時、妙に心にひっかかる文章があった。それは 始まりは、いつも肉体である。セックスを含む、目や口や鼻を通しての肉体がすべてを始めるのだ。そしてなりゆきは心である(134頁) という一文。ガツンと後頭部を鈍器で殴られたような気がした。なぜなら、それはとても自然なことでありながら、それまできちんと文章で説明してくれる人がいなかったからだ。そうしたら、文庫本の解説でも森瑶子が同じ箇所を挙げ、同じ事を書いていたので嬉しくなった。 そのような視点から読み直してみると、この作品には詠美の永遠のテーマでもある心と体の問題についての言及が多いことに気づくだろう。 ただ、この作品は賛否両論はっきりと別れるだろう。この装飾過剰とも取られかねない文章表現ははっきりと好き嫌いが別れるところだ。しかし、それでもいいのだ。この小説の一番の理解者は自分だと、私は勝手にそう思っているから。(というよりも、この小説が好きだという人は、自分が一番の理解者って思っている人が多いと思う。それほど不思議な魔力があるのだ、この『熱帯安楽椅子』には。) 主な論文に以下のものがある。 *「肉体の記憶としてのバリ−山田詠美『熱帯安楽椅子』論−」 土屋忍 『日本近代文学』 1996年10月号 119〜135頁 |